
*上写真「名瀬港と奄美市(旧名瀬市)市街地」をおがみ山から望む
(奄美市は今回の皆既日食が見れる最南端の地。ここから1分程見れるとのこと。奄美市から北へ一時間程で奄美本島最北部では約4分とか、、、)
奄美での皆既日食(7/22)まで3ヶ月を切った。アマミーナのプロジェクトの準備の方も佳境を迎えている。イベントの講演者やパフォーマー受け入れ準備は完了。イベントのポスター等の準備も着々と進んでいるものの、アマミーナツアー(7/18〜7/20の2泊3日)参加者の中、皆既日食観測希望の延泊希望者への対応がまだ、というより宿泊地の確保がまだまだ予測がつかない状態。延泊希望者ご自身で延長分の宿並びに帰りの足を確保してのみ延泊可能ということでお願いしているものの、地の利をご存じない方々が、自分自身でそれを対処するのは至難の業。やはりアマミーナ側のお手伝いは不可欠ということになる。そこで下記のようにお勧めしている。
1. 奄美入りと出の交通手段:マルエーフェリー & マリックスライン
1)奄美ー鹿児島間のフェリー利用 (船中にて一泊。約9時間)
2)鹿児島より乗り継ぎで各地へ帰路(飛行機、電車、or 車)
皆既日食直後7/22&23での飛行機での帰りはまず、不可能。そこでお勧めしているのが、船(フェリー。下記写真参照)。東京からも大阪からも奄美へ船が出ていますが、毎日でないことと、やはり東京や大阪からの船での奄美入りは船中に24時間以上と時間がかかるので、これはお金はないが、暇だけはたくさんあるという学生やバックパッカー(古〜い。笑)にのみお勧めの方法で、通常は船を利用するといっても、奄美ー鹿児島間のみがベスト。毎日夜出航。船で一泊して翌朝早くに鹿児島港着というよく出来たスケジュールで、島の人たちがよく利用している方法でもある。(ホテル代一泊の値段で、宿泊と移動が同時にできるという風に考えれば、実は時間的にも実はロスは少ない。)そして鹿児島から各地へ飛行機で、もしくは九州からの参加者は電車や車で各地へお帰りいただくという方法である。ちなみに皆既日食は7/22の午前11時頃の数分間なので、当日に奄美を離れるのは大丈夫。
もちろん外人さん(これも古い表現かも)のように海外からの参加組は、1〜数週間の滞在で、込む時期を外して、7/25&26日以降であれば、それほど帰りの足を心配することもないのですが、、、日本ではまだなかなかですね。
*写真:船舶会社2社の内の1社、マルエーフェリーの船(確か7~8,000トンくらいの大型)
実はこれが一番大変。皆既日食前後の宿はもうすでに昨年2008年で観光業者に押さえられていて、個人でさがすのは無理。浜辺でのキャンプ施設の確保を市の方でやっているが、これも正直あてにならない。一番確実なのは、皆既日食が見れる奄美本島北部での宿泊はあきらめ、カケロマ島を含む南部で宿を取るという方法。(*それでも、インターネットで検索できる宿はたぶん一杯なので、市町村観光案内所のようなところで電話連絡をするのがベスト)ただ奄美大島南部からだとそこから皆既日食の見れる奄美市以北への移動手段をさらに手配する必要がある。等々、、、バックパッカーのように、どこででも寝れるという人以外、また個人での参加ではなく、家族等での参加など、ケースバイケースで宿の対処方法は異なってくることと思うので、まずはアマミーナ実行委員会へ要相談というところでしょうか。(*何れにしろ、6月に入るまではプロジェクト準備のため、これらのご相談にはアマミーナも対応できない状態です >_<,,,)
3. とびっきりの裏技:
奄美に入るのではなく、沖縄へ。そして沖縄をベースに船で皆既日食前後に奄美入り。沖縄ー奄美間は同フェリーにて。時間は鹿児島ー奄美間とほぼ同じ。
以上です。上記の情報が少しでもお役にたてれば幸いですが、、、
以下奄美への交通手段の一般情報へのサイトリンクです。
*その他奄美大島の情報(ウィキベディアサイト)はここをクリック!








*以下の写真上段左から:私の母の実家、加計呂麻島(かけろまとう)の村落、芝(しば)のタンマの浜(子供時代、この浜辺の座って、海行く船を眺めながら未来を考えていたものでした、、、/古代の自然「ヒカゲヘゴ」原生林/名瀬港を望む/マングローブカヌーツアー
*下段左から:息子、海の腕とその上のトカゲ/瀬戸内(せとうち)側から大島海峡を望む/ハイビスカスの花/水族館の珊瑚








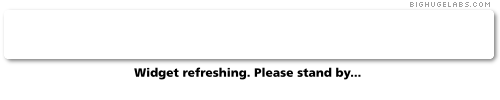











 チコから州のハイウエイ99号線を南下すること約30〜45分ほどで、オーロビル市の郊外、テーブルマウンテンという火山の溶岩が浸食されてできたという高台(台地)の自然保護区がある。チコ市は2月の初旬、アーモンドの木にサクラのような白い花が先始まる頃から、春の装いが始まるが、ここテーブルマウンテンは野草の宝庫で、3月の中旬〜後半がちょうど旬。4月の中旬はもう春の終わりに近い。それでも色とりどりの野草が風に揺られながら背一杯(そうそういう感じで)咲いていた。
チコから州のハイウエイ99号線を南下すること約30〜45分ほどで、オーロビル市の郊外、テーブルマウンテンという火山の溶岩が浸食されてできたという高台(台地)の自然保護区がある。チコ市は2月の初旬、アーモンドの木にサクラのような白い花が先始まる頃から、春の装いが始まるが、ここテーブルマウンテンは野草の宝庫で、3月の中旬〜後半がちょうど旬。4月の中旬はもう春の終わりに近い。それでも色とりどりの野草が風に揺られながら背一杯(そうそういう感じで)咲いていた。








 チコ市で本年2009年度のサイエンスフェアーのセレモニーが4月2日(木)に展示会場で開催されました。今年は、個人、グループ作品全部で約500件のサイエンス作品参加があったようです。
チコ市で本年2009年度のサイエンスフェアーのセレモニーが4月2日(木)に展示会場で開催されました。今年は、個人、グループ作品全部で約500件のサイエンス作品参加があったようです。









 写真左はうちの裏庭にあるひときわ目立つ椿の木。この時期いつも見事なくらい真っ赤は花を咲かせます。うちの回りにも椿が(中古の)家を買った時から植えられていて、他にピンク、白、斑入りのピンク、そして斑入りの赤、全部で4種類。写真には写っていませんが、その右後ろにはサクラの若木も。引っ越し来てから植えた一重と八重。右の写真は同僚、美術史のAsa(エイサ)の一人娘、Lela (リラ)。超かわいい (^_^)。彼女は、米国と中国のダブル(ハーフとは言いたくないので、2つの文化を持つという意味で、私は個人的にこういうことにしている。半分という言い方がなんとなく好きでないので、細かいかもしれないけど、、、)
写真左はうちの裏庭にあるひときわ目立つ椿の木。この時期いつも見事なくらい真っ赤は花を咲かせます。うちの回りにも椿が(中古の)家を買った時から植えられていて、他にピンク、白、斑入りのピンク、そして斑入りの赤、全部で4種類。写真には写っていませんが、その右後ろにはサクラの若木も。引っ越し来てから植えた一重と八重。右の写真は同僚、美術史のAsa(エイサ)の一人娘、Lela (リラ)。超かわいい (^_^)。彼女は、米国と中国のダブル(ハーフとは言いたくないので、2つの文化を持つという意味で、私は個人的にこういうことにしている。半分という言い方がなんとなく好きでないので、細かいかもしれないけど、、、)
