

春である。サイエンスプロジェクトの春がやってきた。海もジョンもプロジェクトにパニクる春でもある。アメリカの学校は小学校からやたらプロジェクトが多く、通常の宿題のように復習や予習をこなすというより、リサーチ(調査&研究)を課される課題がやたら多い。その内の一つがこれ「サイエンスプロジェクト(つまり理科の実験プロジェクト)」
もともと海の学校関係のこと(宿題等々)やめんどうは母である私はほとんど関知しないで、ジョンが見ているのだけど(私ではもう手に負えない >_<,,,)、このサイエンスプロジェクトは特に熱心に見てあげている。ジョンの専門が環境科学で、仕事先がNature Center (自然科学センター)で自然科学の教育プログラムを学校に提供するというようなものらしいから(私も実はよくだんなの仕事をわかっていないの)、特に熱心にめんどうを見ている。海も海でさすがに小さい頃からジョンのおかげで自然に慣れ親しんでいるから、こういったサイエンス関係のプロジェクトにはまじめに取り組んでいる。ということで親子一緒になって力(りき)が入っているのがこのプロジェクト。
去年(4年生の時)の題材が「Does the depth of a seed affect the germination? (土に埋める深さは発芽に影響を与えか?)」で、今年(5年生)のテーマが「Does Light Affect Plant Stomata?(光は植物の気孔作用に影響を与えるか?)」というものらしい。もうこの辺で私にはちんぷんかんぶん。よくもまあ5年生くらいで、こんなテーマでよくやるわいと思う。でもたぶん他の生徒はこんなにまじめに取り組んでいないと思うけどなあ。良い意味、海の場合、熱心なのは「好きこそ物の上手慣れ」という見本みたいなものかなあ。間違いなく、これはジョンの影響。私のDNAでないことだけは確か。私の役目は、実験結果のレポートとしてカーボードにうまくディスプレイーするののお手伝いくらい。一応美術の先生なので、私は私でここで力(りき)が入ります(笑)。
このプロジェクトは学校にまず提出後、良い物は市の展示へ回されるとのこと。そこでまたいろいろな賞が与えられるらしい。そこがまたアメリカ的。(2年前は何かを培養させるような実験で1等賞をもらって表彰されてみたいだけど、去年は私のサバティカル休暇で日本に滞在してチャンスを逃した。今年はどうかなあ、、、というか本人は賞をもらうかどうかは正直どうでも良くて、こういう実験そのものが好きみたいね。良い事、良い事 ^_^) *下記その気孔(Stomata)を顕微鏡で見た写真とのこと(海より提供)

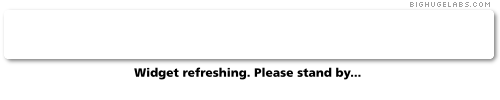
0 件のコメント:
コメントを投稿