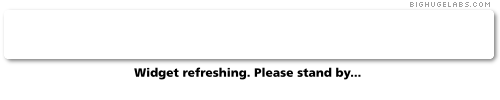2009年9月21日月曜日
最近始めたこと「AM ヨガ」
2009年9月11日金曜日
About District 9:映画「District 9」について
 一人で映画を見に行ってきた。特に見たいものがあったわけでもなく、9/10(木)はFurlough(無給休暇)を取っていたので、たまには一人で映画でもと思い、手頃なものを映画館サイトで探していた中で見つけた「District 9」。
一人で映画を見に行ってきた。特に見たいものがあったわけでもなく、9/10(木)はFurlough(無給休暇)を取っていたので、たまには一人で映画でもと思い、手頃なものを映画館サイトで探していた中で見つけた「District 9」。2009年9月8日火曜日
オバマから子どもたちへのメッセージ:Obama advises caution in what kids put on Facebook
2009年9月4日金曜日
カリフォルニア州経済破綻(其の二):「Furlough (無給休暇)」のお知らせ自動返信メッセージ
Faculty members:
Use This As Your
Email Signature or
Out of Office Reply
「あなたのEメールのサインや自動返信にこれを使ってください。」
This year the CSU is suffering the most severe budget cuts in the history of the University. Our Administration is attempting to manage these cuts by increasing student fees and requiring employees to take unpaid
furlough days.
「今年、カリフォルニア州立大学システムは、大学始まって以来の最も困難な財政危機に直面しています。大学側(経営サイド)は、この危機に対して、学生の授業料アップならびに教員/スタッフ全員に強制休暇(自宅待機:給与カット)を取らせることで乗り切ろうとしています。」
As a result I’m out of the office more often than usual and unable to reply to your e-mail messages as quickly as I would like. I will try to answer your message as soon as is possible.
「その結果、通常以上にオフィスを留守にすることが多くなり、メールでの問い合わせに迅速に対応することができなくなります。可能な限りあなたからのメッセージに迅速に回答するよう努力いたします。」
To learn more about faculty furloughs please visit
「教員(ファカルティー)強制休暇に対する情報についての詳細はこのサイトをご覧ください。」
Thanks,
INSERT YOUR NAME
AND WHATEVER OTHER INFO YOU USUALLY
INCLUDE IN YOUR EMAIL SIGNATURE
ぶっちゃけた話「大学側の決断で経済危機の対応として給与カットの強制休暇を強要されているので、その結果大学を離れることが多くなり、メールの対応も遅れがちになることをご承知置きください。」というもの。つまり、みんなにこの状態を知らしめようというもの。う〜ん。
2009年9月3日木曜日
カリフォルニア州経済破綻(其の一):州立大学は今

2009年8月29日土曜日
アメリカでの映画考察: PG13見せるの見せないの?どっち?
 お昼過ぎ、残暑にぼーっとしながらタイプを打っていると、電話がなった。海の友達から、映画のお誘い「『GI Joe: The Rise of Cobra』を見に行くので、もしよかったら、、、」とのこと。あいにく海はジョンとエアーショーを見に行って留守。海に伝えるわねとそのまま電話を切った後、ジョンの携帯へメッセージを入れておく。帰ってきた海にその旨伝えると大喜びで電話を。もちろん行くとの返事で、そのままジョンと代わって、友達のお母さんと確認の話をしている。その話し振りから、ジョンがあまり乗り気でなさそうなことが雰囲気で伝わってきた。「どうしたの?良くない映画なの?」の私の問いに、「知らないの?コミックが元だけど、バイオレンスだらけだよ。信じられない。子供だけで見させるなんて。」との返事。
お昼過ぎ、残暑にぼーっとしながらタイプを打っていると、電話がなった。海の友達から、映画のお誘い「『GI Joe: The Rise of Cobra』を見に行くので、もしよかったら、、、」とのこと。あいにく海はジョンとエアーショーを見に行って留守。海に伝えるわねとそのまま電話を切った後、ジョンの携帯へメッセージを入れておく。帰ってきた海にその旨伝えると大喜びで電話を。もちろん行くとの返事で、そのままジョンと代わって、友達のお母さんと確認の話をしている。その話し振りから、ジョンがあまり乗り気でなさそうなことが雰囲気で伝わってきた。「どうしたの?良くない映画なの?」の私の問いに、「知らないの?コミックが元だけど、バイオレンスだらけだよ。信じられない。子供だけで見させるなんて。」との返事。 慌てて、映画館のホームページでレートを見てみると、うっ「PG13 (*Parental Guidance 13 の略:13歳以下の子供にはお勧めない映画であるという評価)」が付いている。グーグルサーチで最新映画の専門家批評サイトの「Rotten Tomatoes」を見てみるとさらに悪い。評価度は37%で、専門の批評家全体の合意点は「コミックファンにはノスタルジックだけど、ストーリも良くないし、ヴィジュアル効果も矛盾だらけ(While fans of the Hasbro toy franchise may revel in a bit of nostalgia, G.I. Joe: The Rise of Cobra is largely a cartoonish, over-the-top action fest propelled by silly writing, inconsistent visual effects, and merely passable performances.)」とさんざん。
慌てて、映画館のホームページでレートを見てみると、うっ「PG13 (*Parental Guidance 13 の略:13歳以下の子供にはお勧めない映画であるという評価)」が付いている。グーグルサーチで最新映画の専門家批評サイトの「Rotten Tomatoes」を見てみるとさらに悪い。評価度は37%で、専門の批評家全体の合意点は「コミックファンにはノスタルジックだけど、ストーリも良くないし、ヴィジュアル効果も矛盾だらけ(While fans of the Hasbro toy franchise may revel in a bit of nostalgia, G.I. Joe: The Rise of Cobra is largely a cartoonish, over-the-top action fest propelled by silly writing, inconsistent visual effects, and merely passable performances.)」とさんざん。 これはいかんとジョンと相談して、やはり断りの電話を入れることにした。聞いたら、親はその映画の内容を良くわかっていなかったみたい。代替の子供向け映画「Shorts (*これも同サイトでチェックしたら45%と低い評価、でもまあPGのレートなので、GIよりもましということで)」もあるけどと遠回しに勧めてみたけど、既に子供たち同士で連絡しあって、行くことになっているので、そのまま行かせるよりしょうがないとのこと。う〜ん、どうすべきか迷ったけど、やはりだめなもはだめだよねと決めた。もちろん海はすごーく不機嫌になって、部屋に引きこもってしまった。
これはいかんとジョンと相談して、やはり断りの電話を入れることにした。聞いたら、親はその映画の内容を良くわかっていなかったみたい。代替の子供向け映画「Shorts (*これも同サイトでチェックしたら45%と低い評価、でもまあPGのレートなので、GIよりもましということで)」もあるけどと遠回しに勧めてみたけど、既に子供たち同士で連絡しあって、行くことになっているので、そのまま行かせるよりしょうがないとのこと。う〜ん、どうすべきか迷ったけど、やはりだめなもはだめだよねと決めた。もちろん海はすごーく不機嫌になって、部屋に引きこもってしまった。そりゃ11歳の男の子にとって、アクション一杯の映画はバイオレンスがつきもので、わくわくするのは承知。(そういうママもそういった映画は決してきらいじゃない。むしろ結構好きかも。頭を使わずに見れる映画は楽だし、爽快だものね。ジョンは馬鹿にするけど、「ターミネーター(オリジナル版)」なんて、今でもドキドキよ。正直のところ。)
だけど、君たちぐらいの年は、その影響を受けやすいのも承知。現実と想像の世界が時々一緒になっちゃうもの。遅かれ早かれそういった映画を見ることになるのだろうけど、少なくとも今はまだだめだよ、海君。私たちも不注意だったのは、認める。海が喜び勇んで電話をかける前に、映画のタイトルから内容を確認しておけばよかったね。私たちも少し反省(>_<,,,)。 それにしても、アメリカって国は、出版物のコミックの内容に対しては、コミックコードとかでやたらうるさいくせに、映画には甘いのはなぜ?PGのようなレーティングシステムがあるけれど、実際にはチケット売り場でそれをチェックとかしないので、効果的に機能しているとはとても思えない。結構野ざらしだなあ。大丈夫か?
2009年8月27日木曜日
うちのジョンのブログ:Jon's Journeys

うちのジョン。うちのパパ、もしくはだんな。アメリカ人。現在41歳。(いろいろなエスニックが混じっているらしく、ちょっとみにはアメリカ人には見えないかも。)「ジョン」と呼ぶより「パパー」と呼ぶことが多い。「僕は海の父親だけど、君のパパではないからね」と言われたことがある。時々理屈っぽい。
「うちのジョンはね〜」と奄美の友人に話していたら、「うちのジョンって犬みたいね。」と言われた。そう言えばそうだなあと思ったので、犬でない証拠に皆に紹介することにした。ついでに、その時習っていた奄美の蛇三線(じゃみせん)で島唄をみんなの前で披露したら「うわーすごいわね〜。」と褒めてくれたので、犬でないことは証明できたみたい。もうだいぶ前のことである。
ジョンに会った第一印象として、「アメリカ人というより日本人みたいな人だね」とよく言われる。「日本人みたい」ってどういうことだろうといろいろ考えて見た。どうも普通のアメリカ人とは違うねということらしい。じゃあ「普通のアメリカ人」ってどういう人のことを言うのだろう、と考えていたら、日本人のアメリカ人に対する一般的な印象というのが良くわかってきた。要するに「はーい皆さん元気〜!」というように、やたら明るく、愛想をふりまく、フレンドリーな人々というのが、どうも皆の持つアメリカ人ってことらしい。
確かにそういうイメージからはかなり遠いのがうちのジョン。寡黙な人である。だからといって無愛想では決してなく、人の会話に対してよく微笑んで聞いている。私から言わせると外面がよいだけだと思うのだけれど、この寡黙で優しそうな態度がやたらと友人受けしている。
(そういえば、「一家に一人ジョン」とも言われている。昔あったアメリカドラマ「大草原の小さな家」のお父さんよろしく、家の修理や片付けをまめにしてくれるから。島口(奄美の方言)でいうところの、「まりがるな人(「じっとしていないでよく動く&働く人」という意)」である。母もそういう風にジョンのことを言っている。そういえばである。)
ということで、私の友人たちの結論は、ジョンと私は逆転の関係で、ジョンがより日本人的で私がアメリカ人的なのだそうである。私としては、いろいろ反論はあるけれど、アメリカの水が合っているのは確かなので、今しばらくは、そういうことにしておこう。(そう言えば、家での役割も一般的な男女の反対を行ってる。これの説明をすると長くなりそうなので、また今後。)
ジョンについて書くつもりだったわけではないのに、、、いつものようにどうでもいいことに時間をとってしまった。今日は、ジョンのブログ「Jon's Journeys」をここに紹介したかったのだ。
この私のブログの右上にも掲載されているジョンのブログ。名前の通り旅行日誌的なブログで、旅先の出来事やエピソードを写真を中心に彼のコメントを添えて紹介している。改めて今回よく読んでみたら、これが結構おもしろい。私と違ってリンクで情報をつなげていくのではなく、ページに写真をずらっと並べて、旅先のことがいろいろと紹介されている。ひとつひとつの写真の中に、ジョンならではの視点があって、日本人ではちょっと気づかないような、おもしろい情報が満載である。特に日本社会にあふれている Jinglish (Japanese English:一見英語なんだけど、実際の英語としては意味がなりたたない日本語英語)についてのコメントが傑作である。短い簡単な英語でコメントが書かれているので、英語を勉強したい人にもちょうど良いレベルだと思うので、よろしかったら時々のぞいてみてくださいね。
2009年8月25日火曜日
偶然ばったり宮崎さん(8/18/08)その二


偶然ばったり宮崎さん(8/18/08)その一

とにかくその日、ドアを開けてスーツケースを出そうとしていたら、手伝ってくれていた友人の娘の渚(なぎさ)ちゃんが「徳さん見てー!」と指差す方向に目を向けて見ると、白い帽子を被った男の人がてくてくと歩いているではないですか。後ろ姿をぼっーと見ながら「だーれ?知っている人?」と聞いてみると、「宮崎さ〜ん!」と一言。(後から聞いた話しなんだけど、なんと彼女の家の前を宮崎さんがよく通るのだそう。でもここんとか半年くらいご無沙汰だったとか。)
追いついた宮崎さんの横に並びながら歩き、息をきらせながら、突然呼び立てたことのお詫びをまず言い、10年ほど前に取材をしたことがあること、そのお礼を一言いいたかったこと、アメリカで宮崎さんの作品をこれからも楽しみにしています、と慌ただしくご挨拶をしたら、声をかけた瞬間は何事かと言わんばかりの驚きの顔をしていた宮崎さんが、にこっと例の笑顔で一言「お忙しそうですね。がんばってください。」と言ってくれました。(渚ちゃんが後で、宮崎さんてあんな風に優しく笑うんですね、とも言ってくれたので、笑顔で対応してくれたのは確かよ〜。とよいふうに勝手に解釈しています。)
本当になんという偶然。こういうこともあるんですねというお話しでした。
実はこれには続きがあって、チコに帰ってきて友達 (ジャズピアニストのしげみさん)にご挨拶の電話を入れたら、「雅美さ〜ん、今週末ポニョを見に行くんだけど、行きます?」というお誘い。ということで、今日ポニョを見てきました。ディズニーの配給という肝いりで、吹き替えも豪華だったけど、吹き替えのポニョの歌が少しラップになっていたのは、やはりアメリカだからでしょうか。(それはそれでおもしろかったけど、やはり日本語版をみてみたいです。)Rotten Tomatoesの批評も90%と高かったですね。でもきっと賛否の意見は二つにわかれると思う。批評文も多少なりともポジティブな意見が90%という意味で、「千と、、、」の時とはこのポジティブ感が違うというのは正直あります。ちなみにこれを最後と決めていたらしい宮崎さん、実は日本での興行売り上げが「ハウスの動く城」に届かなかったことを知り、次回を考えているそうです。しばらくはまだ宮崎さんの作品を見れそうです(^_^)。
2009年7月29日水曜日
2009年7月25日土曜日
美内さんとシモベ達(アマミーナ少女マンガ部会)
 終わった〜。アマミーナプロジェクト最後のイベント、クロージングトークとも言える美内すずえさんのトーク「美内すずえ&島んちゅ」と題してが、今日奄美文化センターで開催(1−2時)。昨日一日奄美のユタ神様が降りてくる湯湾岳(宇検村側から)そして瀬戸内町加計呂麻(カケロマ)島を巡り、母の実家のある芝で一泊。早朝市内に帰ってくるという強行軍。それでも前から行きたいとおっしゃっていたカケロマをさっとでも回れてよかった。カケロマは神高い島でもある。
終わった〜。アマミーナプロジェクト最後のイベント、クロージングトークとも言える美内すずえさんのトーク「美内すずえ&島んちゅ」と題してが、今日奄美文化センターで開催(1−2時)。昨日一日奄美のユタ神様が降りてくる湯湾岳(宇検村側から)そして瀬戸内町加計呂麻(カケロマ)島を巡り、母の実家のある芝で一泊。早朝市内に帰ってくるという強行軍。それでも前から行きたいとおっしゃっていたカケロマをさっとでも回れてよかった。カケロマは神高い島でもある。何はともあれ、トークも盛況の内に終わり、もちろん少女マンガ部会で美内さん歓迎の宴を「ほこらしゃ」にて開催。この写真はその最後に皆でぱちりの場面。美内さんを囲んでメンバーの幸せそうな顔、顔、顔。(プロジェクト報告は Visualpopculture Blog 内の項目「アマミーナ」でしますね。このブログTokuToku Journeyではその裏のお話し ^_^)
明日の朝早く、美内さんを空港までお送りし、展示会の撤収作業に入る。奄美でのイベント、アマミーナプロジェクトはこれでオシマイ。(とはいうものの、私は東京国際交流基金東京本部ギャラリーにて再び「4コママンガ展示会」を立ち上げる作業が待っている >_<,,, 私の夏はまだ終わらない。)
2009年7月23日木曜日
いきゅんなかな:奄美より旅立つ人へ贈る言葉:
2009年7月22日水曜日
2009年7月22日奄美にて皆既日食雲厚し
2009年7月11日土曜日
2009年7月10日金曜日
ネリヤカナヤ10周年公演:アシビにて(6/27/09)
2009年7月5日日曜日
坪山豊さんもう一曲:よいすら節
2009年7月4日土曜日
アマミーナイベント:唄者「坪山豊」祝い唄
2009年7月2日木曜日
アマミーナTシャツ少女マンガ版:キュートな女性用もできるかも
アマミーナ少女マンガT−シャツ紹介その一:男女兼用版

奄美大島泥染皆既日食祝いT−シャツ




 今日アマミーナ実行委員会メンバーで和太鼓部会の野崎さんの作る泥染T−シャツの作成行程を見学してきた。アマミーナプロジェクトのメンバーのために、特別T−シャツを作ってくれていて、私も欲しいと追加注文をしたら、その後すぐに「徳さん、せっかくなので、実際にどのような感じで作られているか、見学に来てみませんか?」の電話が野崎さんからあった。「行く行く〜」と即答して、30分後に車で迎えにきてもらい、早速その泥田を見学しにいった。
今日アマミーナ実行委員会メンバーで和太鼓部会の野崎さんの作る泥染T−シャツの作成行程を見学してきた。アマミーナプロジェクトのメンバーのために、特別T−シャツを作ってくれていて、私も欲しいと追加注文をしたら、その後すぐに「徳さん、せっかくなので、実際にどのような感じで作られているか、見学に来てみませんか?」の電話が野崎さんからあった。「行く行く〜」と即答して、30分後に車で迎えにきてもらい、早速その泥田を見学しにいった。一言「よかった〜」。大島紬行程のたいへんさと複雑さは聞いていたし、またその様子を見学させてもらったことはあったけれど、同じ行程でのT−シャツ作成を見させてもらうのは初めて。いや〜参りました。全く同じように手間ひまをかけて作られているのですね。
*写真は野崎さんのご両親とアマミーナプロジェクトのために特別に作ってもらった和太鼓倭(やまと)バージョン皆既日食デザインTシャツ。最終的にこの皆既日食デザインの中心に「倭(やまと)」の文字が入ります。右の赤のハートマークが入ったTシャツは子供用のみの特別デザインだそう。そして大人と同じ行程で手間ひまかけて作られていますが、特別に子供サイズということで、2千円でわけてくださるとのこと。
黒に見えますが、実は黒に限りなく近い焦げ茶です。ティーチ木(車輪梅:しゃりんばい)を煮出した液で20回そして奄美特有の鉄分を多く含んだ泥田で染め上げるという行程を2回繰り替えるとこういう色になります。(つまり40回以上の染の行程)ちなみにこのTシャツは通常6千円のところを4千円という安値で特別に作ってもらいました。ラッキー!