 今日海のクラスの親御さんに展示会のお誘いのメールを出した。学年末の美術教育の学生の展示会に併せて、こどもたちも参加してくれた「4コママンガアート展:Children's Views-What's Going on in Our World?」を開催するにあたってのご招待。
今日海のクラスの親御さんに展示会のお誘いのメールを出した。学年末の美術教育の学生の展示会に併せて、こどもたちも参加してくれた「4コママンガアート展:Children's Views-What's Going on in Our World?」を開催するにあたってのご招待。一人の親御さんから返事が来た。娘は今回出せなくで申し訳なかったとのこと、そして前回参加してとても楽しかったとのこと。返事を書こうとしてジョンに話しをしたら、「その子確か原因不明の病気でこの数ヶ月お休みしているはずだよ。」とのこと。胸が痛んだ。知らなかった。
その子は確か親子でオランウータンの保護を訴えていて、その子の前回の絵は森林伐採でオランウータンの森がなくなっていることを描いていた絵じゃなかったけ。図録を見てみたら、載っていた。優れた作品のひとつに選ばれていた絵だった。
そのあとすぐに返事を出した。今週末まで待てるので、もしよかったらそして娘さんが興味があったら、描いてみませんかと。今その返事を待っている。出してくれるとうれしいな。
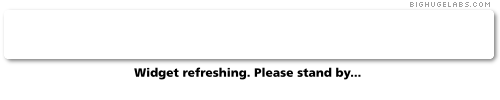






































 ここ数日続いた雨模様にどうなることかと心配していた今日の海のお誕生日パーティ。チコの東側に位置するパラダイス市の先にかっこうのそりスポットがある。そこでの雪そりパーティ。(海の誕生日は1/27なのだけど、日をずらして週末にパーティ。)今日は昨夜までの雨が嘘のように朝からピーカンの青空。車2台でドライブすること約1時間。チコ市内の緑の景色からすっかり雪景色の風景へ。海の仲のよい同級生6人を招待して、午後一杯雪ぞりとランチパーティ。海の友だちの一人のお母さん、レベッカもボランティアで車を一台出してくれた。スポットに着くなり、ランチの準備。ジョンが今朝早くからぐつぐつやっていたコーンスープをキャンプ用ストーブであっためて、サンドイッチをみんなでほおばる。ランチを早々と済ました後はもち子ども達はそり遊び。ノンストープのそりに直滑降、そしてごろごろ(笑)。2時間程やった後、ホッとチョコレートブレイクにバースティケーキタイム。私たち大人はなーんもやってなかったのだけど、なぜかとっても疲れた一日でした。(でも楽しかったよ〜 ^_^)
ここ数日続いた雨模様にどうなることかと心配していた今日の海のお誕生日パーティ。チコの東側に位置するパラダイス市の先にかっこうのそりスポットがある。そこでの雪そりパーティ。(海の誕生日は1/27なのだけど、日をずらして週末にパーティ。)今日は昨夜までの雨が嘘のように朝からピーカンの青空。車2台でドライブすること約1時間。チコ市内の緑の景色からすっかり雪景色の風景へ。海の仲のよい同級生6人を招待して、午後一杯雪ぞりとランチパーティ。海の友だちの一人のお母さん、レベッカもボランティアで車を一台出してくれた。スポットに着くなり、ランチの準備。ジョンが今朝早くからぐつぐつやっていたコーンスープをキャンプ用ストーブであっためて、サンドイッチをみんなでほおばる。ランチを早々と済ました後はもち子ども達はそり遊び。ノンストープのそりに直滑降、そしてごろごろ(笑)。2時間程やった後、ホッとチョコレートブレイクにバースティケーキタイム。私たち大人はなーんもやってなかったのだけど、なぜかとっても疲れた一日でした。(でも楽しかったよ〜 ^_^)



