 観光客でにぎわうショッピング通りの中、それも資本主義の象徴とも言えるマクドナルドの隣、カジノホテルの2階にその博物館はあった。その名も「Communism Museum (共産主義博物館)」。うーんエスプリというか超皮肉。博物館の入場料も資本主義的(結構高い!大人180KC=$11/子供120KC=$7)。古びた廃校の2階という雰囲気でチェコの共産主義の歴史がレーニン&スターリンの銅像と共に時代を追って説明されていた。6カ国語でラベル表示。チェコ語、ドイツ語、英語がメインに、その下にフランス語、スペイン語、&イタリア語が一回り小さく表示。(ちょっと感激)
観光客でにぎわうショッピング通りの中、それも資本主義の象徴とも言えるマクドナルドの隣、カジノホテルの2階にその博物館はあった。その名も「Communism Museum (共産主義博物館)」。うーんエスプリというか超皮肉。博物館の入場料も資本主義的(結構高い!大人180KC=$11/子供120KC=$7)。古びた廃校の2階という雰囲気でチェコの共産主義の歴史がレーニン&スターリンの銅像と共に時代を追って説明されていた。6カ国語でラベル表示。チェコ語、ドイツ語、英語がメインに、その下にフランス語、スペイン語、&イタリア語が一回り小さく表示。(ちょっと感激)改めてチェコという国が第一次世界大戦後まで存在しなかった国であることを再確認。そうなのである。オーストリアハンガリー大帝国の中心に位置していて、その中心としてプラハという街が花開いたのだ。プラハの街の財産はその時のものである。高校時代世界史を習ったときは年表の羅列でそれぞれの時代や歴史を実感することなくひたすら覚えるだけで、ちぃーっともおもしろくなかった(いやいや実はすごーく退屈だった)。実際にその国に来てその国の文化というか空気に触れてみると、始めてその歴史の重さを実感することができるものですね。
話しがそれたけど、未だに共産主義と社会主義の違いがよくわかっていない私ではありますが(実は資本主義の理念もわかっているようで、、、というレベル)、チェコがどうして共産主義になっていったのかも、ここでよく理解できた。私的感想だけど、決してイデオロギーの勝利というようなものではないと思う。生きるためのパン欲しさに目の前に出された救いの手が共産(社会)主義だったというのが本当のところだ。それも20世紀初頭のあのアメリカのブラックフライデー(株価急落)の結果で。それまでは両イデオロギーの中で揺れ動いていてどちらかというと社会主義よりだったとはいえ、中道だったのではないか。ある一つの事件(時としてささいな)が引き金でどっーと歴史が動いてしまうというのは世の常でアル。それまでたまっていたものが、それをきっかけに溢れ出てしまう。それがどの方向に流れるのかは神様だけが知るのみ。ここの博物館の中ではその共産主義時代の生活や教育も写真パネルや関連物で知る事ができたけど、芸術の世界の中でも「Social Realism (社会主義リアリズム) 」の意義を再確認出来たような気がする。アメリカではこの派はどちらかというと美術史の中で無視されがちだけど、再評価されてもよいのではないかと思う。プロパガンダに利用されたとは言え、その中でも夫々のアーティスト達はそれぞれの個性をその中で表現していると思う。(私の「鑑賞学」の教科書の中ではちゃんと語ろうと思う。)
感想。一言予想以上に面白かった。この後頭の中でイデオロギーと美術なんて比較論がごちゃごちゃになって渦巻いてしまった。この後今日のメインだったはずのアールヌーボーの旗手ムッハ(Mucha)の美術館へ。感想。予想通りよかった。そして日本人ツアー客がたくさんいた。さすが日本でも人気のアーティスト。作品はアールヌーボーの特徴である装飾的デザインと優美な女性が中心だったけど、その中でマッハがアーティスト人生の後半自分にアイデンティティーに目覚めてスロバキア的民族以上のデザインを多く描くようになってからのものが必見。その中女の子がきっとこちらを睨みつけるようにペンと本を持って立っている絵が一番印象的だった。なぜか奈良美智さんのナイフを持つ女の子を思い出してしまった。
この2つのミュージアムで今日は目一杯。この後最後の締めくくりはプラハの中心広場のゴシック教会の中でのクラシックコンサートへ。今回は弦楽器の他ピアノにトランペットそしてボーカルが入る。もちろんよかったのだけど、先日の弦楽五重奏があまりにもよかったので、今回はそれほど感激しなかった。何事も最初の印象が第一番というところでしょうか。プラハ最後の日。美術館(博物館)巡りをして最後にやはりクラシックで締めくくったのでした。
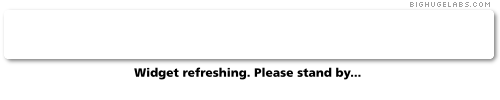
0 件のコメント:
コメントを投稿